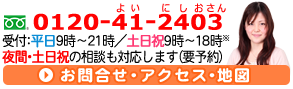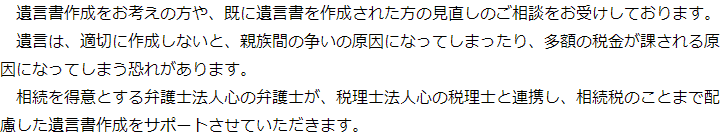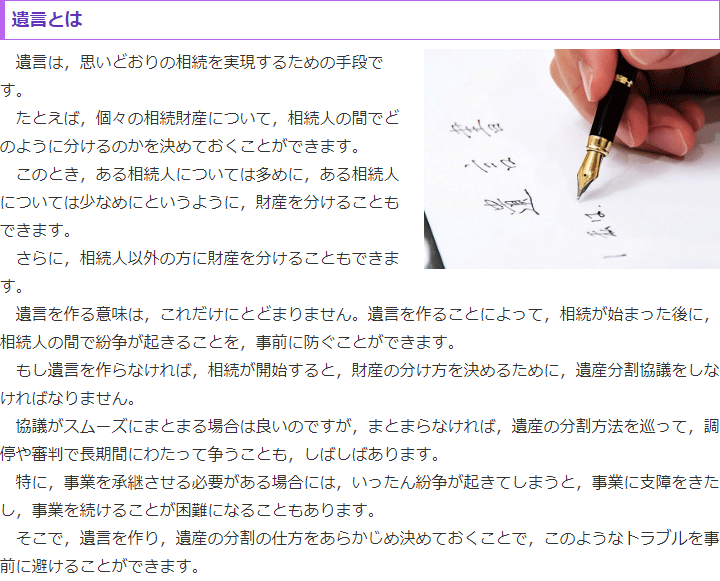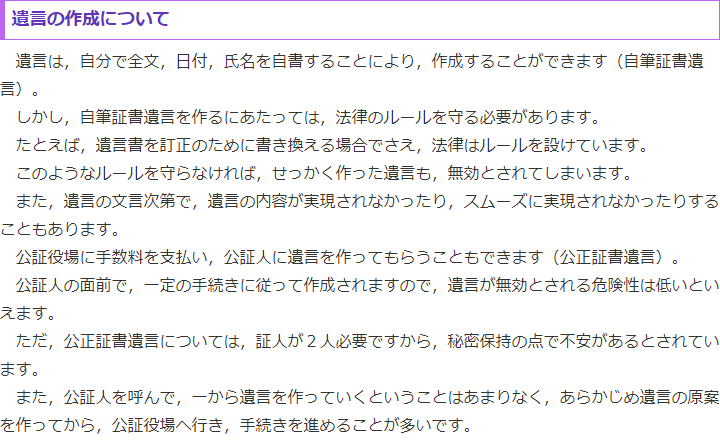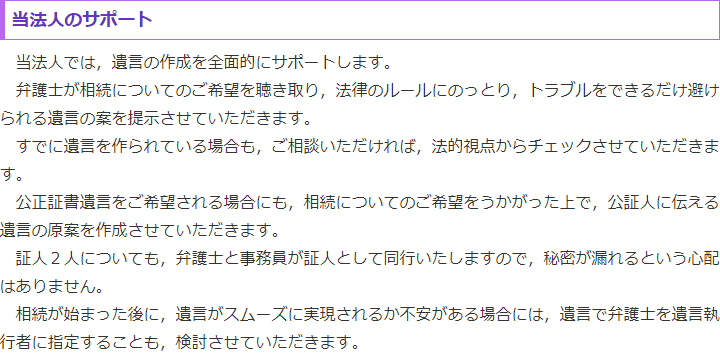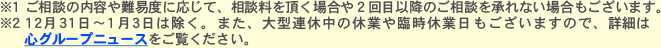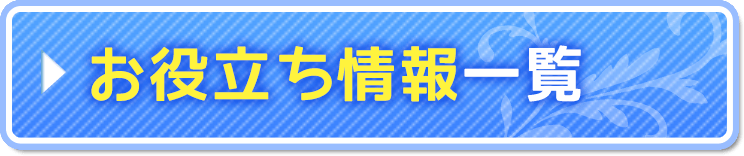遺言
遺言執行者の選び方
1 遺言執行者の権限と義務

遺言執行者は、遺言内容を実現することを役割とする者のことです。
遺言は、遺言者が亡くなった後に効力が発生し、その内容を実現する必要が生じます。
そして、その遺言内容を実現するためには、誰かが行動する必要があります。
その役割を果たすのが、遺言執行者になります。
遺言執行者は、遺言内容を実現するため、遺言の対象となった財産について排他的な管理権限を持つこととなります。
もし、相続人が遺言内容に反する行動を取ろうとしても、遺言執行者は、排他的な管理権を持って、相続人の妨害を排除することができます。
このような強力な権限を有する反面、遺言執行者は、一定の義務を負うこととなります。
具体的には、遺言執行者は、任務を開始した場合には、遅滞なく、遺言執行者に就任したことを通知しなければなりません。
そして、遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する義務も負うこととなります。
また、遺言の趣旨に従って、中立的な立場で職務を行う必要があります。
2 遺言で遺言執行者を選ぶ場合
遺言執行者は、遺言で指定することができます。
「誰々を遺言執行者に指定する」と定めることもできますし、「誰々に遺言執行者を選ぶ権利を与えるものとする」と定めることもできます。
そのため、多くの場合は、遺言で、特定の人を遺言執行者に指定しています。
また、遺言者は、自由に遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者が相続人であってもなくても、遺言により財産を取得する人であってもなくても、遺言者であれば自由に指定することができます。
遺言執行者に指定する人について、弁護士資格等、何らかの資格が必要になるわけでもありません。
もっとも、遺言執行者は、先述のとおり、強力な権限を有する反面、一定の義務を負うこととなります。
このため、相続人間の対立が強く、慎重に権限を行使したり、義務を履行したりすべき場合があります。
このような場合には、遺言執行者は、法的知識を有する専門家を指定した方がよいのではないかと思います。
遺言者が亡くなった後に、遺言執行者に指定された人が、遺言執行者に就任することを承諾した場合には、正式に遺言執行者に就任し、遺言執行者の職務を果たすこととなります。
3 家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう場合
遺言で遺言執行者に指定された人が、遺言執行者に就任することを拒絶した場合には、新たに遺言執行者を選任する必要が出てきます。
遺言で遺言執行者に指定された人が、すでに死亡していたり、認知症に罹患していたりする等の理由により、遺言執行者としての職務を行うことができない場合についても同様です。
これらの場合は、相続人の管理権が復活するわけではなく、新たに遺言執行者を選任する必要があることとなりますので、注意が必要です。
このように、新たに遺言執行者を選任する場合には、遺言者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所で選任申立てを行うこととなります。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てた場合、誰を選任するかは家庭裁判所が決めることとなります。
実務上は、遺言執行者の選任申立をした人が、遺言執行者の候補者を挙げ、その候補者がそのまま遺言執行者に選任されることもあります。
なお、遺言で遺言執行者の指定がなされていないものの、遺言内容を実現する上で支障が生じている場合についても、遺言執行者を選任することができます。
遺言の作成に必要な費用
1 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、紙、書くもの、印鑑があれば、すぐに作成することができます。
このため、自筆証書遺言を作成する際には、費用負担はいらないということになりそうです。
しかし、現実には、ご自身で遺言を作成したものの、遺言に不備があったために、無効になってしまったといった例が存在します。
遺言の不備が発覚した時点では、多くの場合、遺言を作成した人は亡くなってしまっています。
そのため、遺言が無効になったので遺言内容を実現することができず、法定相続人で分割しなければならなくなるという、取り返しのつかない事態が生じてしまいます。
この点を踏まえると、遺言を作成する際には、まず、遺言の文案を作成し、専門家にチェックしてもらうか、専門家に希望を伝え、専門家に文案を作成してもらうのが適切であると言えます。
それでは、専門家に文案をチェックしてもらったり、文案を作成してもらったりするには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
この点については、個々の専門家によってまちまちです。
定型的なものですと、数万円の費用負担になることが多いと考えられますが、定型的なものでなかったり、複雑な内容のものだったりすると、数十万円の費用負担になることもあります。
2 公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、公証人に対する手数料が必要になります。
参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
手数料は、遺言の目的となる財産額や公正証書の枚数によって変わってきます。
また、公証人に出張を依頼する場合、証人の手配を依頼する場合は、これらの費用も必要になってきます。
公正証書遺言を作成する際には、あらかじめ、公証人との打合せを行う必要があります。
事前に公証人に公正証書遺言の文案を提示しておくと、公正証書遺言の作成がスムーズに進むことが多いです。
このような、公証人との打合せ、文案の作成については、専門家に依頼することもできます。
この場合には、専門家に支払う費用も必要となりますが、遺言に関する希望を伝えれば、あとは専門家が手配を行ってくれますので、安心して遺言を作成することができます。
専門家に支払う費用は、先述の自筆証書遺言の場合と同額程度であることが多いでしょう。
遺言書を作成する際の注意点
1 遺言を作成する際の注意点
遺言を作成する際には、何点か注意すべきポイントがあります。
以下では、いくつかの具体例を挙げて、遺言を作成する際の注意点について説明したいと思います。
2 手続がスムーズにできるかどうか

遺言では、主として、誰がどの財産を取得するかをあらかじめ決めておき、将来の紛争を抑止するために作成されます。
この点を明確に決めておくと、将来の紛争が回避でき、一安心と感じられる方が多いように思います。
もっとも、現実には、遺言を作成しておいたものの、遺言によっては相続の手続を行うことができないといった事態が生じてしまうことがあります。
こうした場合には、結局、相続人全員の協力を得て、手続を進めざるを得ないこととなりますが、協力を得られず、手続が止まってしまうということも多いです。
このため、遺言を作成する場合には、手続がスムーズにできるかどうかに注意する必要があります。
たとえば、相続人以外の人に財産を遺贈するとの遺言を作成したとします。
この場合、遺言執行者が指定されていなければ、財産の遺贈を受けた人は、相続人全員から実印の押印、印鑑証明を得て、手続を進めなければならなくなります。
相続人全員の実印の押印、印鑑証明を得ることができないと、訴訟等によって手続を進めることも検討せざるを得なくなってしまいます。
このような事態を避けるためには、相続人以外の人に財産を遺贈するとの遺言を作成する場合には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
3 予備的条項に留意する
遺言により財産を受け取るものとされた人が、遺言を作成した人よりも先に亡くなった場合、どうなるのでしょうか?
この場合、先に亡くなった人が受け取るものとされていた財産は、原則として宙に浮いてしまい、相続人全員で遺産分割を行わなければならないこととなってしまいます。
このため、その他の相続人も権利主張し、財産を受け取ることができることとなってしまいます。
現実には、遺言により財産を受け取るものとされた人が先に亡くなられた例は、しばしばあります。
その後も遺言の書き直しがなされず、先に述べたような事態になってしまうこともあります。
また、遺言を作成した人が判断能力を失ってしまっており、そもそも、遺言の書き直しをしようとしてもできない例も存在します。
その後、遺言を作成した人が亡くなってから、問題を解決しようとしても、解決する術は失われてしまいます。
こうした事態を避けるためには、遺言により財産を受け取るものとされた人が先に亡くなった場合には、他の人に相続させるという、予備的条項を設けておくべきでしょう。
相続人がもめない遺言を作成するためのポイント
1 遺言について相続人がもめる場合

遺言を作成したとしても、相続後に相続人がもめてしまい、裁判になってしまうこともあります。
このように相続人がもめる場合として、2つの場合があります。
1つ目は、遺言自体の有効性が争われる場合であり、2つ目は、遺留分侵害額請求がなされる場合です。
ここでは、それぞれについて、もめない遺言を作成するためのポイントを説明したいと思います。
2 遺言自体の有効性が争われる場合
遺言内容について、不明確な点がある場合には、遺言自体の有効性が争われることがあります。
また、作成された遺言が、本当に遺言者自身が作成したものかどうかが分からないとの主張がなされることもあります。
他には、遺言を作成した当時、遺言者が判断能力を失っていたとの主張がなされることもあります。
このようなもめ事を避けるためには、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか?
まず、遺言内容について不明確な点が生じることのないよう、専門家に遺言内容をチェックしてもらうことが考えられます。
次に、遺言者自身が作成したものであることを明らかにするために、遺言を作成している様子を写真や録画で残しておくことも考えられます。
さらに、遺言者が認知症に罹患している等、遺言者の判断能力の有無が争われる可能性がある場合には、医師の診断書を得ておいた上で、遺言を作成することが考えられます。
このように、もめない遺言を作成するためには、ただ単に遺言を作成するだけでなく、作成時に様々な準備を行っておくことが望ましいと考えられます。
3 遺留分侵害額請求がなされる場合
遺言で特定の相続人が遺産のすべてまたはほとんどを取得するものとした場合には、他の相続人から、遺留分侵害額請求がなされることがあります。
このような請求がなされることを避けるためには、他の相続人についても、遺言で、遺留分相当額の財産を取得するものとしておくことが考えられます。
また、他の相続人については、生前贈与がなされているため、そもそも、遺留分侵害額請求を行うことができない場合があります。
このような場合には、他の相続人がすでに生前贈与を受けていることを遺言に付記しておくことにより、遺留分侵害額請求がなされることを回避することができる可能性があります。
遺言作成にあたって遺留分にお悩みの方へ
1 遺言を作成するにあたっては、遺留分に留意した方が良いことがある

自身が有する財産を、将来、希望する人に引き継ぐこととしたい場合には、遺言を作成することが考えられます。
遺言を作成することにより、特定の人に対して、遺言者が有するすべての財産を引き継ぐものと定めることもできますし、特定の財産のみを引き継ぐものと定めることもできます。
どのような遺言を作成するかは、遺言を作成される方の自由です。
もっとも、遺言を作成するにあたっては、遺留分の存在に留意すべき場合があります。
相続人は、法律上保障された最低限の相続の権利として、遺留分を有しています。
このため、相続人は、遺言によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができる場合があります。
以上のとおり、遺言によって財産を取得した人は、ただ財産を取得して終わりとなるわけではなく、一定の債務を負ってしまうこととなる可能性があります。
2 遺留分侵害額請求がなされる可能性がある場合の対応策
遺留分侵害額請求がなされる可能性がある場合には、遺言によって財産を取得すべき人がなるべく十分に財産を引き継ぐことができるよう、一定の対策を取っておいた方が良い場合があります。
こうした対策について検討するにあたっては、特定の人に財産を引き継ぎたい理由がどのようなものであるかという点に立ち返った方が良いでしょう。
たとえば、特定の相続人が、遺言者と同居しており、遺言者の介護等を行っているため、その相続人に財産を引き継がせたいと考えることがあると思います。
このような場合には、遺言による財産の引継ぎだけではなく、生前贈与による財産の引継ぎも検討した方が良いでしょう。
生前贈与による財産の引継ぎの方が、現に介護等がなされている時期に財産が交付されることとなりますので、介護等に対する謝礼という側面にも合致しやすいでしょう。
加えて、相続の10年以上前になされた贈与については、遺留分の算定の基礎となる財産には含まれないこととなっています。
このため、早い段階から前倒しで生前贈与を行うことにより、その財産が遺留分算定の基礎となる財産に含まれなくなり、遺留分侵害額請求によって支払わなければならない金銭を減少させることができる可能性があります。
3 遺言についてのご相談
このように、遺言を作成する際には、将来、遺留分侵害額請求がなされる可能性があることを念頭に置きつつ、遺留分対策をとっておいた方が良いことがあります。
もし、遺言についてご相談事がありましたら、お近くの弁護士までご相談ください。
専門家による遺言の調査方法
1 遺言の調査の必要性

相続の手続きを進める大前提として、最初に遺言の有無を調査する必要があります。
遺言の調査が不十分ですと、相続の手続きを進めた後、遺言の存在が明らかになるという事態が発生してしまいます。
このような事態が発生すると、多くの場合、すでに行った相続の手続きが無効になってしまいます。
このような理由から、遺言の調査は、相続の手続きを進める上で不可欠の前提になります。
2 公正証書遺言の調査
公正証書遺言については、各地の公証役場において、被相続人が作成した遺言が存在するかどうかを検索することができます。
参考リンク:日本公証人連合会・亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?
このように、公正証書遺言の検索を行えば、必ず公正証書遺言が存在するかどうかを調査することができます。
もっとも、裏返せば、公正証書遺言の検索を行わない限り、自分が把握していない公正証書遺言が存在するかどうかを確認することができないこととなります。
このため、公正証書遺言が存在することに気付かずに、相続手続きを進めてしまうことがしばしばあります。
専門家は、相続人から委任を受けましたら、公証役場において、公正証書遺言の検索を行うことができます。
3 自筆証書遺言の調査
自筆証書遺言については、法務局で保管されている場合は、法務局で、被相続人が作成した自筆証書遺言が保管されているかどうかの申請を行うことにより、自筆証書遺言の有無を調査することができます。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度(相続人等の手続き)
この申請についても、相続人から委任を受ければ、専門家が代理人として行うことができます。
問題は、法務局で保管されていない場合に、どのようにして調査するかです。
この場合は、特定の相続人が遺言を託されて保管しているのでなければ、被相続人が保管している蓋然性の高い場所を網羅的に確認する以外の方法はありません。
それでは、被相続人が保管している蓋然性の高い場所は、どのようなところなのでしょうか?
基本的には、被相続人の自宅の、貴重品等が保管されている場所を確認することとなります。
親族に託されている場合もありますので、念のため、親族に確認する必要もあるでしょう。
他には、銀行と貸金庫契約を行っている場合には、貸金庫に保管されている場合もありますので、貸金庫の開扉手続きが必要になることもあるでしょう。
遺言について専門家に相談するべきタイミング
1 遺言に関心を持ったら、すぐに遺言を作成すべき

遺言についての相談は、いつするべきなのでしょうか?
結論としては、遺言に関心を持ったら、すぐに遺言を作成するべきだと思います。
ここでは、遺言をすぐ作成するべき理由について、説明したいと思います。
2 遺言の作成は先送りになりがちである
遺言に感心を持ったとしても、実際に作成するのは先でも良いと考え、結局、作らないままとなってしまうことが多いものと思います。
遺言の作成は、感覚的には、緊急性のあることではありませんので、すぐに作らなければという動機付けを行いにくいものと思います。
また、いざ遺言を作成するとなると、過去の出来事や将来の生活等、様々なことを考慮しなければなりませんので、かなりのエネルギーが必要になります。
このため、結局、まだ遺言を作らなくても良いと考えてしまいがちであり、先送りになりなってしまう傾向があります。
3 遺言を作成するタイミングを逃すと取り返しがつかない
このように遺言の作成を先送りにすると、取り返しがつかない事態が生じることもあります。
過去の事例でも、遺言の作成を先送りにした結果、本人が認知症に罹患し、遺言を作成することができなくなったという例もありました。
このように、本人が遺言を作成できなくなってしまうと、相続対策を行うことはほぼ不可能になり、取り返しのつかない事態に陥ってしまいます。
遺言が作成できなければ、基本的には、相続人全員で合意をしなければ、不動産や預貯金、有価証券等の相続手続を行うことができなくなってしまうからです。
また、基本的には、権利主張を行う相続人に対して、相続分に基づいて、相続財産を分割する必要も生じてきます。
このように、遺言が作成できなければ、相続問題は、格段に錯綜した状態になってしまうおそれがあります。
4 遺言についてのご相談
結論としては、遺言の作成を先送りにしてしまい、タイミングを逃してしまうような事態が生じることを避けるためにも、遺言に関心を持ったら、すぐに遺言を作成するようにするのが望ましいでしょう。
当法人は、過去に、多くの遺言作成に関与しており、スピーディーに遺言の案文を作成し、遺言の作成を提案することができる体制を作っています。
遺言についてのご相談事がありましたら、当法人までお問い合わせいただけましたらと思います。
遺言に強い弁護士に相談すべき理由
1 遺言問題は作成しただけでは終わらない

遺言作成については、どの弁護士に相談しても、大差ないという話がなされることがあります。
確かに、遺言の問題が、誰がどの財産を取得するかを書いて終わるのであれば、複雑な内容の遺言でない限り、どの弁護士に相談しても、結論に大差はないでしょう。
しかし、実際には、遺言の問題は、作成して終わりではありません。
遺言者が亡くなったあと、遺言内容の実現のための行動が必要になりますし、その過程で、様々な紛争が生じてくる可能性があります。
遺言を作成するのであれば、こうした、遺言内容の実現の場面での紛争回避を念頭に置いて、どのような遺言を作成するかを決めるのが望ましいでしょう。
そして、この点については、弁護士の助言を得るより他ないでしょう。
たとえば、公正証書で遺言を作成したとしても、公証人は、遺言内容の実現の場面での紛争回避についての助言を行うことは、ほとんどないでしょう。
このような、遺言内容の実現の場面での紛争回避について助言を得るためには、弁護士にご相談いただくより他ないでしょう。
ここでは、遺言内容の実現の場面での紛争の例を挙げたいと思います。
2 遺言内容をそのまま実現することが困難な場合
特定の相続人に対して、相続財産のすべてを取得させるとの内容の遺言は、しばしばなされます。
しかし、このような遺言については、他の相続人から、遺留分の主張がなされる可能性があります。
たとえば、子が遺留分の主張を行う場合は、基本的には、法定相続分の2分の1の権利を主張することができます。
さらに、令和2年に施行された改正相続法により、遺留分権利者は、遺留分に相当する金銭の支払を求めることができることとなりました。
このため、相手方との合意が成立しない限り、金銭の支払に代えて、不動産を渡すといった対応を行うことも、できないこととなってしまいました。
したがって、相続財産の多くを不動産が占めている場合は、何らかの方法で、遺留分に相当する金銭を調達する必要があることとなります。
このように、遺言を作成したものの、遺言者が亡くなった後に紛争が顕在化し、遺言によって財産を取得した相続人が追い込まれた状況になる可能性もあります。
こうした事態を避けるためには、遺言を作成する段階で、将来生じる可能性のある紛争を想定し、これへの対策を踏まえた遺言を作成することが望ましいと言えます。
そのためには、遺言に強い弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。
各専門家が協力できることの強み
1 遺言に関係する専門家

遺言に関係する専門家は、様々です。
法律上の問題を洗い出しつつ、法的に問題のない遺言を作成するためには、弁護士に相談するのが望ましいです。
相続財産に不動産が含まれている場合には、遺言によって不動産の名義変更を行うことができるどうかを確認するため、司法書士に相談するのが望ましいです。
相続財産の総額が一定金額以上になる場合には、相続税が課税される可能性がありますので、税理士に相談するのが望ましいでしょう。
このように、遺言に関係する専門家は様々ですので、問題のない遺言を作成するには、各専門家が協力する必要があるといえます。
各専門家の協力が不十分だと、遺言内容を実現できなかったり、想定外の問題が生じたりする可能性があります。
ここでは、各専門家の協力が不十分だったため、問題が生じた実例を説明したいと思います。
2 小規模宅地等の特例を使うことができなかった事例
この事例では、3名の子が推定相続人になっていましたが、いずれの子も、遺言を作成した人とは別に生活していました。
遺言を作成した人が複数の不動産を所有していたため、生前に遺言を作成しておき、それぞれの不動産を誰が取得するかを定めていました。
この事例では、不動産の相続の問題となるため、司法書士に相談し、遺言が作成されることとなりました。
このとき、遺言を作成した人が居住している不動産について、誰に引き継ぐかが問題となりました。
遺言を作成した人が居住している不動産ですので、小規模宅地等の特例の適用対象となり得、限度面積まで、土地の評価額を80%も減額することが想定されていました。
参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
このため、小規模宅地等の特例を用いるため、きちんと誰が取得するかを遺言で決めておきたいという要望がありましたが、子のうちの誰が取得するかについては、こうでないといけないという希望はありませんでした。
このため、遺言では、何となくという理由で、長男が、遺言を作成した人が居住する不動産を取得するものとされました。
その後、遺言を作成した人が亡くなったため、相続人である3人の子で、相続税申告を税理士に依頼することとなりました。
ところが、相続人が税理士に相談したところ、遺言を作成した人が居住していた不動産については、小規模宅地等の特例を用いることができないとの回答がありました。
小規模宅地等の特例を用いることができるのは、被相続人が居住していた不動産を、配偶者、同居の親族、持家を有していない親族のいずれかが取得した場合に限られます。
これら以外の人が、被相続人が居住していた不動産を取得したとしても、小規模宅地等の特例を用いることはできません。
この事例では、配偶者は存命ではなく、相続人全員が被相続人と別居していました。
また、次男・三男には持家がありませんでしたが、長男は持家を有していたため、長男が遺言で不動産を取得すると、小規模宅地等の特例を用いることができないこととなってしまいました。
小規模宅地等の特例を用いることを想定していたのであれば、被相続人が居住していた不動産は、持家を有していない子に引き継ぐべきだったのです。
このような事態を避けるには、遺言を作成した段階で、税理士にも相談し、小規模宅地等の特例を用いることができるかどうかを確認すべきだったといえます。
逆にいえば、各専門家の協力のもと遺言を作成すれば、このような事態が生じることは防げたでしょう。
このように、各専門家が協力できることは、ご希望の遺言を作成するために必要な知識を網羅的に得ることが期待できるという点で、強みになるということができます。
遺言について専門家に相談する際の流れ
1 遺言内容についての希望を共有する

遺言作成を専門家に相談するに当たっては、どのような内容の遺言の作成を希望するかについて、専門家と意識を共有する必要があります。
そのためには、前提として、どのような内容の遺言を作成するかについて、希望をまとめておいた方が良いでしょう。
このとき、ポイントとなるのは、誰にどの財産を引き継ぐか、あるいは、誰にどのような割合で財産を引き継ぐかです。
不動産が複数ある場合や、金融資産が複数の金融機関や証券会社にある場合で、それぞれを別々の相続人に引き継ぐことを希望さる場合には、メモ形式で、それぞれの財産を誰に引き継ぐかをまとめておくと、相談がスムーズに進むでしょう。
最初の相談の段階での希望は、暫定的なものでも構いません。
その後、遺言内容についての希望に変化が生じた場合には、変更後の希望を専門家に伝えて、作成する遺言の内容を変更すれば良いでしょう。
2 遺言案を作成する
遺言内容についての希望を共有したら、次は、それを遺言案の形にします。
遺言案については、文言の使い方等、注意すべき部分が多々あります。
この点については、専門家に委ねるのが良いでしょう。
遺言の本文とは別に、相続人に対するメッセージを残したい場合には、付言事項として、遺言案に付け加えることもあります。
こうした付言事項を付け加えておくことにより、遺言に込められた真意を相続人が理解する可能性もあります。
付言事項を付け加えることをご希望の場合は、付言事項の文案も作成いたします。
3 遺言を作成する
上記の文案に基づいて、実際に遺言を作成します。
遺言については、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれかが作成されることが多いです。
自筆証書遺言の場合は、遺言を作成する方が、基本的には、全文を自書する必要があります。
ただし、遺言に添付する遺産目録に限っては、一定の条件を満たせば、パソコンで打っても構わないこととなっています。
誤記があると、遺言が無効になってしまうこともありますので、自筆証書遺言の場合は、作成後に専門家にチェックしてもらうのが望ましいでしょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場に問い合わせ、公正証書の作成を依頼します。
この場合、上記の文案を公証役場へ提出すると、公正証書作成までの流れがスムーズになるでしょう。
遺言で困った場合の相談先
1 遺言の相談

遺言作成の専門家と言うと、どのような専門家が思い浮かぶでしょうか?
近年では、様々な専門家が遺言作成に関与しているという話を聞かれる方もいらっしゃるかもしれません。
それでは、一体、遺言の作成を検討するときには、誰に相談するのが望ましいのでしょうか?
ここでは、遺言の相談をするための専門家を選ぶためのポイントを、いくつか挙げたいと思います。
2 将来の遺言執行を見据えた遺言の作成
遺言は、相続が発生した後に、実際に遺言に書いた内容を実現できるかどうかが、非常に重要なポイントになります。
遺言で遺志を伝えた後には、実際の相続の段階で、その遺志を実現する手立てが必要不可欠になります。
万一、実際には遺言の内容が実現できないということになると、遺言者が希望しない事態が生じてしまうでしょうし、このことが、かえって争いを深刻にしてしまうおそれもあります。
したがって、遺言を作成するにあたっては、将来の遺言執行を見据えて遺言を作成する必要があります。
例えば、不動産や金融資産などの財産については、その財産を相続する人が遺言で指定されている場合は、その財産を相続する人だけの印鑑で足りますが、そのような遺言書がない場合は相続人全員の印鑑が必要になることがあります。
そのため、遺言を作成するのであれば、このような相続手続きの際、他の相続人の印鑑を得なくても、遺言に基づいて手続きができるような内容にすることが望ましいでしょう。
遺言執行を念頭に置いた遺言になっていなければ、他の相続人の印鑑を得なければ、遺言内容が実現できないといった事態も起こり得ます。
3 将来生じる可能性のある法的問題を念頭に置いた遺言の作成
実際に遺言内容を実現する段階では、様々な法的問題が生じるおそれがあります。
遺言を作成するにあたっては、将来生じるかもしれない様々な法的問題を見据えつつ、遺言を作成するのが望ましいといえます。
例えば、特定の人が遺言者のすべての財産を取得するという遺言を作成したい場合を考えてみましょう。
そういった遺言を書いた際でも、一部の相続人には「遺留分」という、最低限度の遺産をもらえる権利がありますので、他の相続人がその権利を使い、遺留分侵害額請求をする可能性があります。
遺留分侵害額請求がなされると、原則として、遺留分相当の金銭を一括で支払わなければならなくなります。
このような場面では、どのようにしてその金銭を準備するかが、重要なポイントになってきます。
対処法としては、保険契約を組んでおき、保険金から支払を行うことなどが考えられますが、これらの対処策を用いるには、遺言を作成する段階から対応策を検討しておく必要があるでしょう。
4 望ましい相談先
これらを前提とすると、遺言を作成する際には、ただ、遺言の文面についてだけでなく、将来の遺言執行や、将来生じる可能性のある様々な法的問題をきちんと把握し、アドバイスができる専門家に相談するのが望ましいということになります。
この点から、遺言を作成する際の相談先としては、これらの問題をきちんと把握している弁護士が適切であるといえます。
遺言に基づいて農地の名義変更をする場合の注意点
1 農地の名義変更

農地を相続する場合には、農地の名義変更を行う必要があります。
農地の名義変更は、その農地を管轄する法務局で登記申請を行い、登記簿上の名義人を変更します。
伊勢市にある農地を相続した場合は、伊勢支局で申請を行うことになります。
参考リンク:法務省・津地方法務局 伊勢支局(いせしきょく)
なお、相続した農地の名義変更を行う際には、注意しなければならないことがあります。
まず、農地の名義変更の場合には、一定の例外を除いて、農業委員会の許可を得なければならないとされています。
そして、登記簿上、田や畑になっている土地については、一定の例外を除いて、農業委員会の許可書を提出しなければ、登記申請が受理されないこととなっています。
登記簿上、農地になっている土地について、遺言に基づいて名義変更を行う場合も、農業委員会の許可が必要になる場合があります。
このように、農地については、相続したものの、農業委員会の許可を得ることができないために、名義変更ができないということが起こり得ます。
このため、農地の名義変更をするには、前提として、農業委員会の許可を得ることができるかを検討する必要がある場合があります。
以下では、この点について、場合分けをして説明を行いたいと思います。
2 相続させる遺言の場合
遺言によって、自身が所有している農地を、誰かに引き継ぐものと定めている場合があります。
「相続させる遺言」とは、相続人に対して、遺産の全部または一部を引き継ぐものとしている遺言です。
農地を取得する人が相続人であり、遺言で「●●に相続させる」という文言が使われている場合には、相続させる遺言に該当します。
相続させる遺言は、遺産分割の仕方を定めるものと解釈されていますが、相続人が遺産分割によって財産を引き継ぐ場合には、農業委員会の許可は不要であるとされています。
このため、相続させる遺言によって相続人が農地を取得した場合には、農業委員会の許可を得る必要はないということになります。
なお、相続させる遺言は、相続人が財産を取得する場合のみに認められています。
遺言の文言が「●●に相続させる」になっていたとしても、取得する人が相続人以外である場合には、下記の遺贈する遺言に読み替えられることとなっています。
3 特定遺贈する遺言の場合
「特定遺贈する遺言」とは、ある人に対して、特定の財産を遺贈するものとする遺言です。
特定遺贈は、相続人に対しても、相続人以外の人に対しても行うことができます。
遺言で「●●に遺贈する」という文言が使われている場合には、特定遺贈する遺言に該当します。
「●●に渡す」「●●に譲る」といった文言が使われている場合も、特定遺贈する遺言に該当すると解釈されます。
特定遺贈は、遺言を作成した人から受遺者への財産の譲渡と考えられています。
このため、特定遺贈により農地を取得した場合には、農業委員会の許可が必要になると考えられていました。
もっとも、相続人が特定遺贈を受けた場合は、相続させる遺言によって引き継いだ場合と実質的な違いは小さく、相続させる遺言と取り扱いを区別する理由が乏しいといえます。
このため、2016年以降は、相続人が特定遺贈を受けた場合に限り、農業委員会の許可を得る必要がないことになりました。
一方、相続人以外の人が特定遺贈を受けた場合には、依然として、農業委員会の許可が必要とされています。
4 包括遺贈する遺言の場合
「包括遺贈する遺言」とは、ある人に対して、遺産の全部または一定割合を遺贈するものとする遺言です。
「すべての財産を遺贈する」「財産の3分の1を遺贈する」と定める場合がこれに該当します。
包括遺贈は、相続人に対しても、相続人以外の人に対しても行うことができます。
包括遺贈は、相続人に類する地位を得るものになりますので、相続した場合と同じく、農業委員会の許可を得る必要はないということになります。
5 農業委員会の許可は必要なくとも届出は必要
ただ、農業委員会の許可が必要ないとはいえ、農地を相続したことを農業委員会が把握できなければ、農業委員会が適切な管理を行うことが難しくなってしまいます。
そのため、許可は必要なくとも、農業委員会への届出は必要になりますので、農地の名義変更とあわせて、忘れずに届出を行うようにしましょう。
遺言作成を依頼する専門家選びのポイント
1 遺言作成に必要な知識

遺言については、書籍やインターネットで雛型を容易に入手することができます。
このような雛型を用いれば、容易に遺言を作成することが可能であるように思えてしまいます。
しかし、適切に遺言を作成するためには、状況に応じた配慮も必要になりますし、十分な法的知識も必要になってきます。
ここでは、まず、遺言作成に必要な知識を説明した上で、どのような専門家を選ぶのが適切かを説明したいと思います。
2 形式、書き方に関する知識
遺言は、相続開始後に、相続財産の払戻や名義変更の手続を進めることができるように、作成しなければなりません。
払戻や名義変更の手続に用いることができなければ、遺言を作成した意味の大部分が失われてしまいかねないです。
このため、遺言をどのような形式で作成すれば有効になるか、どのような書き方をすべきかについて、知識が必要になります。
遺言の作成にあたって、雛型を用いる目的も、ここにあります。
もっとも、形式や書き方については、標準的なものであればそれ程問題はないかもしれませんが、しばしば、状況に応じて、標準的ではない形式や書き方を用いる必要があることがあります。
こうした標準的ではない形式や書き方は、雛型だけでは対応が困難です。
そして、こうした問題が発覚するのは、通常、相続が発生した後です。
このような問題の発生を避けるためには、遺言作成の段階で、あらかじめ、詳細な知識を有している必要があります。
こうした知識を雛型で得るのは困難です。
遺言の形式や書き方について、詳細な知識を有している専門家にご相談いただくのが適切でしょう。
3 遺言に関する紛争についての知識
遺言を作成したとしても、遺言無効確認請求や遺留分侵害額請求等の主張がなされ、紛争が発生することがあります。
遺言を作成するにあたっては、こうした紛争を念頭に置きつつ、できれば、こうした紛争の回避、抑制につながる遺言を作成したり、遺言以外での対処策をとったりしておくのが良いと言えます。
こうした紛争は、状況に応じて様々なものがあり、通り一遍の知識で、発生する可能性のある紛争を想定し、適切な対策を立てることは、極めて困難です。
将来の紛争を想定して適切な対策を立てることができるのは、実際にこうした紛争への対処を経験している専門家に限られると言えます。
4 税金に関する知識
遺言により財産を取得すると、いくつかの税金が問題になります。
まず、遺産総額が一定額を超えると、相続税が発生します。
相続税については、誰がどの財産を取得するかにより、課税額が異なってくることがあります。
また、遺言と合わせて生前対策を行うことにより、最終的な課税額を抑制することができることがあります。
できれば、相続税に関する知識を用いつつ、将来課税される可能性のある相続税額をシミュレーションしたり、対策を行ったりした方が良いでしょう。
次に、遺言を用いて不動産を名義変更するにあたり、登録免許税、不動産取得税を納付する必要があることがあります。
登録免許税は、不動産を取得するのが相続人であるかどうかによって、税率が異なってきます。
不動産取得税は、不動産を取得するのが相続人であるかどうかによって、課税されるかどうかが異なってきます。
これらの税金の負担は、不動産の評価額によって変動しますが、数十万円、数百万円の負担になることもあります。
遺言を作成するにあたっては、こうした税金も念頭に置いておいた方が良いと言えます。
遺言について相談するのであれば、税金に関する知識も持っている専門家に相談するのが良いでしょう。